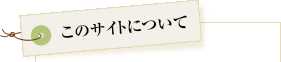旅の合間に・サバイバル時代の海外旅行術 高城剛 光文社新書
2010年2月8日
なんとなく本屋をのぞいていて、上記の本を求めました。1964年生まれの映像作家、こちらは存じ上げなかったが有名な方。その旅とても忙しいものだが、現在の技術を使いこなすとそういうものになるのかと、興味深く拝見しました、そこでその紹介を。
まず旅のことを書こうとすると、どなたもお気付きになるこの国の後進性について。出国は13位、受け入れは30位。鎖国的な政策が、国際競争力の低下と、高齢化による労働力の低下を招いたと言う。さらに出国を人口あたりで見ると日本は0.14回、台湾0.23ニュージーランド0.33。イギリスは1.15回で第1位。しかも若者が減って、老人が増えている。この本では触れていないが、日本の海外旅行の大半がツアーだから、参考にする人は彼が考えているよりはるかに少なくなる。
で最初はガイドブックについて、世界がいかに充実しているかが例を上げて紹介される。それはこちらの旅でも同じことで、仕方なしにロンリープラネットを求めることが少なくない。
ただこれからは大きく違う。こちらは荷物を持って目的地を通過していくがそれは昔風で、今は拠点都市(ハブ)に荷物を預け、手荷物だけで旅行するのが主流になっているらしい。格安航空会社LCC(Low Cost Carrier)ができて、そちらがはるかに安く快適に旅行できると、驚くような実例を上げてみせてくれる。買い物、観光、農家に泊まるアグリツーリズム、そしてレストランなど。
そのためには情報を入手しなければならないが、それはインターネットを使いこなす。その使い方をいろいろ教えてくれる。旅の間も、パソコンは欠かせないことになるが、それと同時に携帯電話もナビゲーターとして使う。その都市で求めて使いこなすと、いかに安く便利であるかが教えられる。
そして最後に、持参する荷物(七つ道具)とパッキングの方法。これは見事だと感心し、真似しようと思うことも少なくない。といって洗たくはしないという彼の方針と、こちらはあまりに違う。
考えてみれば、彼とは時間の持ち具合が決定的に違っているし、またこちらが旅をするのは彼が活用する現代の技術から離れることでもあるのだから、それは仕方のないことだろう。
こちらは気持ちの良さそうなカフェでただぼんやりと坐るために旅をしているみたいなものだし、彼のようにやるべきベスト10を決めてあれもこれもと手に入れるのとははるかに遠い。持ち帰る物にしても、求めてきたCDは情報なしのものが多くてパソコンでは聴きにくいものになってしまう。*
ひとつだけ、このところ世界のハブといわれる空港のソファで寝ている人が結構いて、なぜだろうと思っていたのだが、その理由がなんとなくわかったのはうれしかった。
ま、それぞれにいろんな旅の仕方があることが豊かなことで、彼もそれをすすめている。旅先で会えばいろんな話ができて、結構話が合うだろうと思う。
*わかりにくくてゴメンナサイ。私家版のCDは、それで一括されてしまうので、トラックの番号で並べられてしまう。例えば、こちらのパソコンでは、中国の民謡、クロアチアの音楽祭入賞曲、ロマの演奏が番号順に1曲づつ並んで、どうも聴く気になれない。