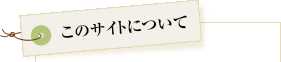旅の準備・1
2010年9月4日
カレンダーをめくって(6枚のうち、残りはもう2枚)、旅の月がスタートしました。旅の準備も本格的具体的にしなければなりません。*遅くなって失礼。相変わらずの暑さで、午後はこちらもパソコンもばてています、部屋が西向きでコッチは何時もの珈琲店か、かき氷の店に逃げ出しています。
まずは少しでも体力をつけておかねばと、朝の散歩を昔の本格コースに戻しました(渦が森の展望公園まで、往復2時間足らず)。といってまだ狂ったような暑さだから、少し早起きして、7時半の出発。緑陰の山道にたどりつくまでの道は、出勤の皆さんとすれ違ってちょっと申し訳ない。Tシャツは早速に汗まみれになってしまう。山道では小枝を振って、クモの巣を払いながら進みます。
公園でシャツを替え、河原で水を触ったりして引き上げる。以前とは30分違うためか、顔なじみの方には会わない。ツクツクボウシが鳴き、瀕死のアゲハがスローモーションで飛んでいる。休日にはキャンプの人がいたり、大型犬を水浴びさせたりしているが、話はしない。帰って水シャワーを浴びる。それでひと仕事終えたような気になるのが欠点です。
ところでヨガの教室で教えられた歩き方によると、足というのは2本に分かれたところからではなくて、もっと上の腰の部分からのようです。ほとんど動かないけれどその部分を左右交互に出すように歩くのが正しい歩き方(これを「腹を割る」と言うのだそうです)。やってみると確かに足が長くなったというか、少なくも太ももの前面が伸びて、歩幅が大きくなったような気がする。ともかく全身運動ということだけはよくわかる。チーターが走る姿とはまるで違うけれど、考えとしてはつながっているらしい。
旅の予定2010秋
2010年8月12日
さていよいよ旅の計画です。
1) まず例年の中国への教育支援ツアー、今年は湖南省。夏休み中でなく新学期に入ってからの9月12日出発で1週間。
21日に打ち合わせがありますから、詳しくはその後に。
2) そして10月はヴェネチア。実は前回新しく完成した安藤忠雄さんの美術館に行こうと思っていたら、秋にある建築ビエンナーレの総合ディレクターに妹島和世さんが選ばれたというニュースが入ってきた。どうせ行くのなら一緒にしたいと、秋に延期した。
久しぶりの建築を見る旅(アーキ トラベル)だからその前後をどうするかだが、それにふさわしいのは文句なしにコルビジュエのロンシャン。地図を見るとミラノを通過してとてもうまくつながる。
さらに発着の空港をどこにするかとその前後をさらに伸ばしていくと、片方はアールヌーボーのブリュッセルに、もう一方は街歩きの番組で行きたくなったスロベニアのリュブリャナにたどりつく。
全体はなんとなく円弧になって「現代建築への円弧」というタイトルまで思いつく。途中のバーゼルやストラスブールに立ち寄る、久しぶりの濃密な旅が実現しそうだ。これなら、誰か誘ってもいい旅になりそうですね。
本の旅・ニッポンの海外旅行 山口誠(ちくま新書)
2010年8月7日
また面白い本を見付けてしまった。副題に「若者と観光メディアの50年史」とあるように、若者を中心としてきたこの国の海外旅行の状況をメディアと関係づけて見事に切り取ってみせている。表紙裏にある紹介文をそのまま書き写してみる。
「最近の若者は海外旅行に行かなくなった」といわれて久しい。二十代の出国者数は1996年にピークを迎え。十年あまりで半減した。それを若者の変化だけで問題化するのは正しくない。海外旅行の形も、大きく変わってきたのである。本書は「何でもみてやろう」「地球の歩き方」「深夜特急」「猿岩石」など、時代を象徴するメディアとそれらが生まれた社会状況を分析し、日本の若者が海外をどう旅してきたかを振り返る。そして現在の海外旅行が孕む問題の本質を、鮮やかな社会学的アプローチで明らかにする。
著者が「地球の歩き方の歩き方」の共著者であったことを知り懐かしく思ったのが、こちらはそういう本を読むことで旅にあこがれ、やっと自分の時間を持つことができて旅をスタートさせた時期が、ちょうど若者の海外旅行が減少していく中であったようだ。道理でと思い当たることも少なくないが、旅とは本来的にその時代の言説や風潮、つまり日常に反抗することで出かけるものだという本質は失いたくないものだ。
また最近の海外旅行で欠かすことのできない現象、例えば、定年退職者を初めとする高齢者の旅行、おばさんなど女性たちのツアー、大学の観光学科(当然、若者が学んでいる)、観光が国の重要政策になっていること(観光客誘致政策)、などについても目配りして欲しかった。
ともかくたまたまのことだがこのブログで紹介した、加藤仁「定年からの旅行術」(現代新書)、高城剛「サバイバル時代の海外旅行術」(光文社新書)と合わせた3冊がお互いを補いあって、この国の現在の海外旅行を語っているように思う。
本の旅・経済について
2010年8月3日
今の世の中、経済で動いている。人は何かあれば、景気を気にする。仕方がないことだろうが、リタイアの身にはちょっと気にしすぎだと感じる。
そこで最近気付いた、まるで違う経済の見方を紹介します。
まず内田樹さん(atプラス03・大人になるための経済活動)。経済とは商品やサービス情報などの交換によって共同体を維持するためにある、言語や結婚(女の交換)と同じ働きに過ぎない。それが金融ビジネスという博打によってゆがめられ、共同体を破壊するようになっているのに、それが経済だと思われている。むしろ贈与経済へ、共同体が維持される方向にお金を使っていくことを考えたらどうだろう、とサッカーのパス(贈与)を例にして語られる。
*こちらは「AERA10.8.2佐藤優・読まずにいられない」から引き写しですが。柄谷行人(世界史の構造)は交換様式として語る。A・互酬(贈与と返礼)~ネーション、B・略取と再配分(支配と補償)~国家、C・商品交換(貨幣と商品)~資本、D・X(例として、社会主義、共産主義、大東亜共栄圏、国連)。具体的に、その先のあるべき方向「X」が模索されているようだ。
この他、思想地図vol.5社会の批評(東浩紀、北田暁大 編集)など、知の世界の人がようやく自動繁殖する資本の横暴に対して、何か言わねばならない。その先を考えねばならないと思われてきたようです。やはり時代は曲がり角を迎えています。
ところで本の旅は今回でしばらく休みにして、次回からいよいよただ今計画中の本当の旅、というか自分の話にします。
本の旅・大沢真幸さんの「もうひとつの1Q84」と「ビッグイシューの挑戦」
2010年7月31日
前回に、その間に読んだ本では、大沢真幸さんの雑誌4号「もうひとつの1Q84」、佐野章二「ビッグイシューの挑戦」、それぞれに面白かったけれど~。と書いたけれど、それで済ますのはちょっと申し訳ないので、少し。
大沢さんは村上春樹を社会学的に読んでいる。理想を追い求めた時代の破綻が見えた70年代の初めに村上春樹は登場した。そして現実を秩序づけるのは情報社会、消費社会と呼ばれる虚構の時代へと移っていく。そのピークが1984年頃と言う訳だ。その視点で作品を読むのはとても面白い。
ところでこちらは「1Q84」を読んでいない(読んだのは、ノルウェーの森まで、あまり読む気がしなくなった)。でも「世界の終りとハードボイルド~」を読んでいたために、あまり不都合なく?理解できた。オウム真理教や世界に広がる原理主義の現実を重ねて、この本を読んでしまう私たちに村上春樹は回答を与えているのか。大沢さんの理解はそこに及んでいて、彼の言う現在「不可能性の時代」に対応していると言う。その論文に続く、辻井喬さんとの対談や参考資料(あらすじまである)も充実している。
*「1Q84」を読まないで、村上春樹について理解したい方にこれほどいい冊子はない。
佐野章二「ビッグイシューの挑戦」はホームレスの人に売ってもらって収入を得てもらうという雑誌だが、もう7年も続いている。その顛末をまとめたもの。その努力に感心するが、何よりこの雑誌を買っていたのが若い女性であったことに驚いた。そこに「不可能性の時代」の夢をまたみることができるようだ。
ともかく生きて世界を見ることができるのは、何にも変えられない幸せだ。